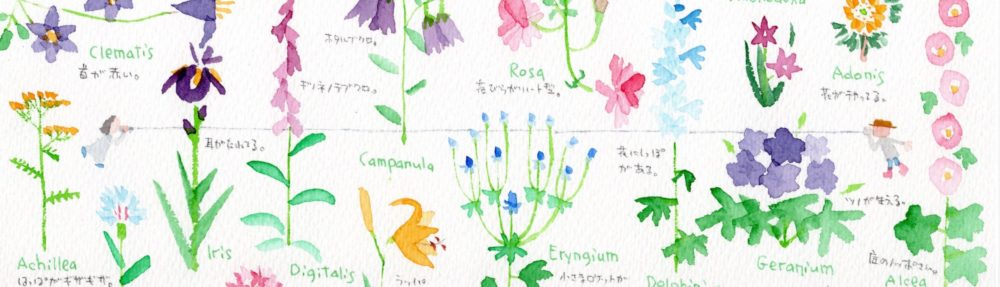村上龍が電子出版の会社を起こしたことで、にわかにニュースに電子出版の話題が増えている。でも電子出版の方法は実は簡単。ワードファイルをgoogleの提供するソフトでE-pubに変換してAppStoreに載せればいいだけだ。村上龍は既存のテキストに、写真やアニメーション、音楽などのマルチメディアをプラスしようと考えているが、そんなことをしなくてもテキストだけで電子出版は成り立つのだ。先述のように簡単すぎて、腰が抜けるくらいだ。
問題は、作者の作ったものがそのまま商品として価値を生むかは別の問題だということ。これまでその商品価値を担保してきたのは出版社にサラリーマンとして帰属する編集者だった。彼らが読者代表として単純な校正や、文章のわかりやすさ(場合によっては逆に分かりにくくすることもある)、適切な全体構成、差別用語のチェック、矛盾のない物語展開、さらには作者が望んでいるテーマをいかに文章で実現するかなどをアドバイスして作者に変更を要請してきた。そしてそれも作者の機嫌を損ねないよう(損ねたら書いてくれなくなる)、まるで作者自身がそう望んでいたかのように作者を思い込ませながら変更を実現するのも編集者の技術として培い、作者の「作品」を商品として成立させてきた。
そういうふうに編集者が作者を甘やかせてきたので、作者は電子出版になれば自分の力だけで作品を流通させることができると思いがちだが、おそらく編集者がつかないと、アングラ以外の作品は成立しない。「生のまま」では、とれたての新鮮な刺身を提供することはできても、料理してお客に振舞う料理店はできないからだ。
それに気づいた作者は、おそらく自分とタッグを組むにふさわしい編集者をスカウトして彼を番頭のようなポジションに置いて出版を始めるだろう。
だが、有能な編集者の数は作者の数より少ない。
ということは、いずれは編集者が複数の作者を抱えた電子出版社を始める。つまり、「編集者=電子出版会社」になるだろう。
さらにその先は、大きな弁護士事務所のように、たくさんの有能な編集者を抱えた「出版社」ができるかもしれないが。